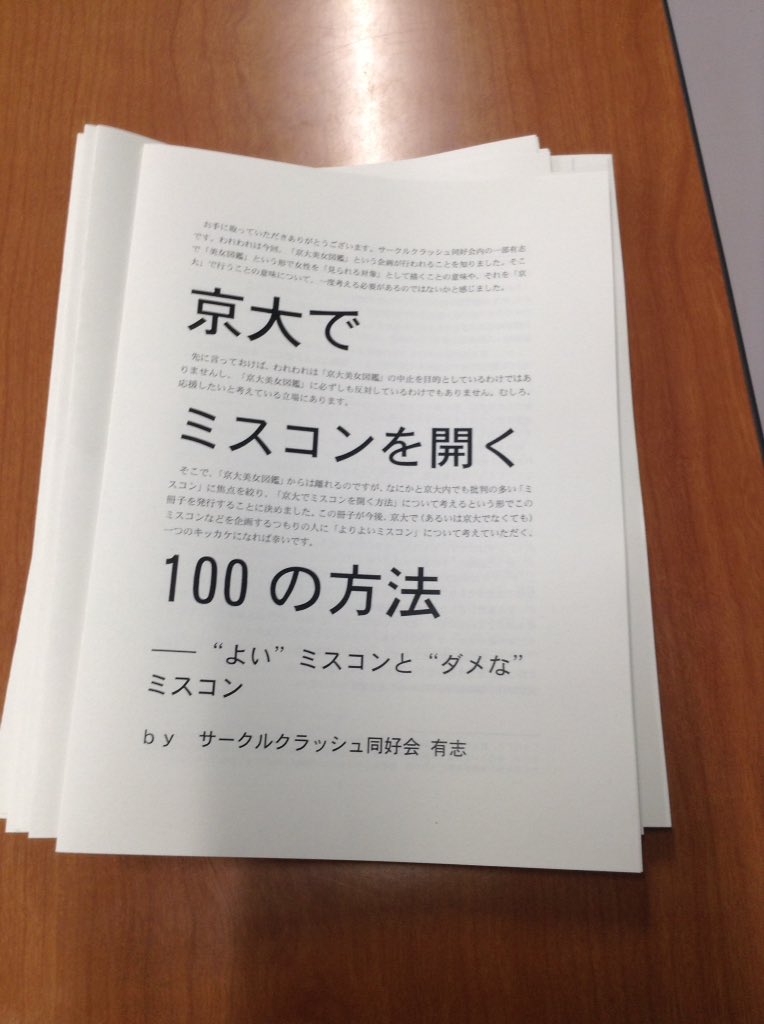ホリィ・センです。このたび、東京の友人の日和下駄くんと一緒に「メンヘラ批評」という同人誌を第二十八回文学フリマ東京 (5月6日(月)11:00~17:00 東京流通センター 第一展示場)で販売することにしました。
まず、「メンヘラ批評」と銘打って何がしたいのかを説明しましょう。それは一言で言えば、なんらかの作品などを「メンヘラ」という切り口から見ることによって、新たな世界の見方を提示し、その見方によって「メンヘラ」をエンパワメントすることを目指す、ということです。
例を挙げるなら、「この映画の登場人物の破天荒な生き様を詳細に描き出してみました。この生き様はこういう点で読者の生き方においても参考になりますよ」ということを提示するといったことです。あるいは、「この小説に出てくる一見頭がおかしい登場人物の行動原理を読み解きました。こういう人も実はまっとうに理解できる考え方で生きているんですよ」ということを明らかにして読者に考えさせるとかです。ノンフィクションを題材にしてもよいでしょう。「なにかのコミュニティでこういう制度があったんですが、そのせいで被害を受けた人がいました。その手口はこういう感じなんでみんなも引っかからないようにしましょう」とかとかです。
しかし、「批評」というと「メンヘラ」を外側から評価して、好き勝手なことを言うような内容を想像する人もいるかもしれません。「エンパワメントすること」を目的とする以上、できるだけ「メンヘラ」に寄り添った内容を目指したいですし、読者を傷つけるような内容は避けようと思います。そのような危険を冒してまで敢えて「批評」という言葉を使う理由はなんでしょうか。
「批評」は「評論」よりも「否定」の意味合いを帯びた言葉です。では、何を否定するのでしょうか。僕たちが今生きているこの社会の抑圧を、です。現代のこの社会で生きづらさを感じている人にとって、「メンヘラ批評」が突破口になってくれれば。そういう思いで敢えて「批評」という言葉を使います。
ということで、「メンヘラ批評」に文章を寄稿してくれる方を募集します。コンセプトの都合上、読者のために作るつもりなので、多少のクオリティは要求しますが、題材としてはなにかの作品(映画、テレビドラマ、小説、エッセイ、自伝、音楽、漫画、アニメ、ゲーム、絵、詩、演劇等々)や社会における出来事、人物、はたまた自分自身のことなど、自分のやりやすいもので大丈夫です。「なんか書いてみたいけど、題材が定まらない」という人は案を出すのを手伝うのでお話しましょう。ご連絡ください(また、後述するように、「メンヘラ系」みたいなジャンルがあると僕は思っていますので、何も思いつかない人はそこから選ぶのがいいかなと思います)。原稿の文字数としては最低2000字程度を考えています。原稿料も出す予定です。
連絡先は、holysenアットマークgmail.comです。Twitter(@menhera_hihyouや@holysen)などに連絡していただいても構いません。
***
しかし、なんでまた「メンヘラ」で同人誌を作りたいのか・作るべきなのか、そもそもなんで「メンヘラ」という言葉にこだわるのか、といった疑問を持つ人もいるでしょう。ということで、ここからはこの「メンヘラ批評」プロジェクトについて考える上での見取り図的なものを示したいと思います(とはいえ、僕が思う「メンヘラ」像に依拠しながら書くことになりますので、できるだけ世間の「メンヘラ」に対するイメージも尊重し、バランスよく記述することを目指しますが、どうしてもバイアスのかかったものにはなってしまいます。そのあたりはご了承ください)。
まず、「メンヘラ」という言葉にまつわる社会の問題(だと僕が思っているもの)を三つ紹介します。そして、どういった対象をどのように見て、何を読者に提示できれば「メンヘラ批評」はその問題の解決に寄与できるのかといったことを三つの問題のそれぞれについて書きます(1~3)。次に、具体的な作品名やアーティストを挙げながら「メンヘラ系」と呼べるようなジャンルの存在を指摘します(4)。そして、「メンヘラ批評」にどういう意義があるのかを考察した後(5)、同様の意義を有した実践例を紹介します(6)。最後に、僕自身の個人的な立場から「メンヘラ批評」を企画した理由を述べたいと思います(7)。
ところで、「メンヘラ」という言葉は何を意味しているのかについては、みなさんいろいろ思うところがあると思います。ひとまず、メンヘラとは「みんなが『メンヘラ』だと思っているもの」だと定義しておきます(定義になっていないと思うかもしれませんが)。というのも、「メンヘラ」という切り口から作品等を見る、というコンセプト上、あまりしっかり定義しちゃうと、「メンヘラ」という言葉がせっかく豊饒なイメージを持っているのに、そのイメージを固定化してしまうのはもったいないからです。
さて、それではまず「メンヘラ」にまつわる問題を三つに分類しながら説明していきましょう。
***
1.「メンヘラ」の個人的生きづらさ
まず、「メンヘラ」というのは、言葉からするとメンタルヘルスer、すなわちメンタルヘルスに問題を抱えた人のことです。例えば、なんらかの精神的なストレスがあると、それが原因となって何かがうまくできなかったり、人間関係がうまくいかなかったり、またそのことが精神に悪影響を与える悪循環になったりといったことがあるでしょう。
こういうことは程度の問題はあれど、みなさん経験したことのあることだと思います。それが「メンヘラ」や「生きづらさ」と呼べるレベルまで達している人も「メンヘラ批評」の読者にはいることでしょう。ということで、なんらかの読者を各々の書き手が想定した上で、その読者が使いこなせるようなライフハック、戦略のようなものを提示することがその解決策になってきます。
もっと言えば、そのような戦略はある種の極端さや過剰さ(ラディカルやドラスティックなどと言ってもいいでしょう)を持っている場合があり、そのことをある種魅力的に描き出すこともできるでしょう。言うならば、「プロ生きづらいマン」の生き様を示すというやり方があると思います。その「生き様」は読者にとって実践的に参考になるというだけでなく、読者に勇気を与えるなんらかの励みになる場合があると考えられます(後に述べるように、それが悪影響をもたらす可能性もありますが)。
この場合、「メンヘラ」的な作品の登場人物やノンフィクションの人物に焦点を当て、その人物の戦略や取りえた選択肢、その「魅力」などを分析することになるでしょう。
2.「メンヘラ」的な社会関係
次に、「メンヘラ」について考える上では人間関係的な側面が付きまといがちだと僕は考えています。親をはじめとした家族との関係がうまくいっていなかったり(例えばいわゆる「毒親」)、恋愛関係や夫婦関係がうまくいっていなかったり(例えば「DV」や「共依存」)といった問題が見出せます。他にも「いじめ」や「ブラック企業」や「洗脳」のようなキーワードに代表される、閉鎖的・権力的・暴力的な関係は「メンヘラ」的な社会関係だと僕は考えています。
他にもいろいろ挙げようと思えば挙げられるかもしれません。このような社会関係における問題に対処するためには、まず実態を理解する必要があるでしょう。そこで、このような「メンヘラ」的な社会関係の「実態」を読者に向けて描き出す、ということがまず考えられます。
しかし、急いで付け加えると、何をもって「実態」と言えるのかは非常に難しいところがあります。例えば、「自分が見た事例はこうだった!」というルポのようなものがあったとして、それがどこまで一般化可能で、読者がその現象を理解する上で役立つのか、といったことを把握するのは難しいわけです。むしろ、一事例を過度に一般化することで、誤った見方を強化しかねないところもあるでしょう。そのため、「実態を明らかにする」という作業には慎重さが求められます。「どのような状況でどのような条件だったのか」というような、全体的な構造をしっかり記述することで客観性を持たせるべきだと僕は考えています。というのも、僕が思うに、ただでさえ「メンヘラ」というものはイメージで語られがちな言葉だからです。
イメージの問題については次で述べるとして、この場合の問題解決策は、作品などに出てくる設定や状況から「メンヘラ」的な社会関係を見出し、その構造やメカニズムを分析するということになるでしょう。
3.「メンヘラ」のイメージに伴うスティグマ
ここまで、「メンヘラ」にまつわる問題とその解決策を二つ述べましたが、それが「問題である」という見方自体は、「メンヘラ」についての「イメージ」によって生じていると言うことができます。この「イメージ」の問題は「問題化されてしまうという問題」、言わばメタ問題なわけです。そして、この「問題化」が特定の個人や集団に適用されて、そのことによって著しい不利を被ったり、攻撃を受けたりする場合、その「問題化」は「スティグマ化」であるとさえ言えるでしょう。スティグマとは「烙印」を意味する言葉で、社会的に差別を受けるような属性のことを指します。つまりこの問題は「メンヘラ」という言葉のイメージのせいで社会からのけものにされてしまうというスティグマの問題です。
「メンヘラ」という言葉はいわゆる「バズワード」であり、指している意味が曖昧であるためにイメージばかりが拡散しています。例えば、人間関係で問題を引き起こしたり情緒が不安定だったりする女性が「メンヘラ女」と呼ばれる事例がインターネット上の一部で見られますが、そのイメージのせいで誹謗中傷を受けたり、自分の不安定な部分を隠さなければいけなかったりといった人もいることでしょう。また、セルフスティグマとして自分を「メンヘラ」のイメージに当てはめることで、自己肯定ができないとか、「自分から不幸になりにいく」ような行動を取るなどといった場合もあるように思います。
この「問題」の解決策としては何が考えられるでしょうか。この場合、例えば「健常者/メンヘラ」のような区別が(インターネットを中心とした)様々なメディアを通じて社会に流通していると考えられます。となると、この境界線を揺らがせるような見方を読者に提示できると良いでしょう。例えば、「認知の歪み」という言葉があります。これは、「完璧主義」「マイナス思考」「レッテル貼り」などの「非合理的」な認知を指したものですが、これらが果たして「歪み」だとか「非合理的」だとか、なぜ言えるのでしょうか。例えば、「マイナス思考」のおかげで慎重になれることで、危険を回避できることだってあるかもしれません。仮にもっと合理的には思えない見方を持っていたとしても、その人の中では主体的にその見方が選択されており、ある意味でそれが最も適応的かもしれないわけです。そういった営みを「歪み」などと「レッテル貼り」すると、むしろその人の主体性を奪っていることになってしまうでしょう。
だからこそ、一見非合理的に見える考え方にもその人なりの論理があるのだということを読者に提示できれば、「非合理的」だとされてきた人のイメージ改善に繋がります(とはいえ、手放しに「非合理的」な考え方や行動を賞賛するのもまた危険だとは思います。おそらく、多様な考え方や行動を選択肢として持っておく、ということが重要なのだと僕は思います)。
逆に、社会的に健常だとされている見方や行動にも「メンヘラ」性が潜んでいることはあるでしょう。ということで、後述する「メンヘラ系」のジャンルには分類されないような作品における「メンヘラ」性を鋭く読み解くという方法もまた考えられます。そうすることで、「健常者/メンヘラ」という区別が実は曖昧であり、両者は地続きであるということを読者に示すことができるかもしれません。
また、区別を保った上で、「メンヘラですがそれが何か?」というある種の開き直りを提示することも可能かもしれません。「開き直り」とまで言わなくとも、「メンヘラ」が他者と異なる存在であることを認めた上で、なおも「そのままでいい」ということがメッセージとして読み取れる作品は数多く存在しているように思います。そういった作品から、なぜ「そのままでいい」と言えるのかを分析して、その説得力を読者に判断してもらうということもできるでしょう。
4.「メンヘラ系」というジャンル
ここまで、「メンヘラ」にまつわる三つの問題の解決について、「メンヘラ批評」がどのように寄与するかを一般的な形で述べてきました。再度ざっくりとまとめ直しますと、①「メンヘラ」を個人に帰属するものとして捉えるならば、その個人の「戦略」や「生き様」を提示する。②「メンヘラ」を関係や集団的なものとして捉えるならば、そのメカニズムや構造を明らかにする。③「メンヘラ」を社会に流通しているイメージとして捉えるならば、「メンヘラ」の持っている論理が理解可能になるよう分析したり、逆に非「メンヘラ」だとされているものに「メンヘラ」性を見出したり、「メンヘラ」を「そのままでいい」ものとして提示したりなどすることで、「メンヘラ」という言葉のイメージの転換を図る。以上の三つになります。
ここまで、みなさんの持つ「メンヘラ」のイメージを固定的なものにしすぎないために、敢えて具体的な作品名や人物名までは出さないようにしてきました。ここからは、「メンヘラ」という切り口を用いたときに対象となるものの具体例として、作品や人物についても焦点を当てていきます。
独断と偏見が混じっていることを承知で書きますが、世間には「メンヘラ系」と言えるようなジャンルが存在しているように思います。あるいは、Twitterなどを見ていると、「メンヘラ界隈」のようなゆるやかなネットワークが形成されているようです(それも一枚岩ではなく、様々な「メンヘラ界隈」が存在するようです)。このような「メンヘラ系」や「メンヘラ界隈」はどのような特徴を元にまとまっていると言えるのでしょうか。先にイメージしやすいように、キーワードを列挙するなら「精神疾患」、「親との確執(虐待)」、「いじめ」、「暴力」、「美醜」、「性(セックス)」、「恋愛でのトラブル」、「自傷(リストカット)」、「死(自殺)」、「向精神薬(オーバードーズ)」、「ドラッグ」、「劣等感(承認欲求)」、「創作表現活動」などが挙げられるかと思います。具体的に見ていきましょう。
先ほどの「メンヘラ」を①個人として/②関係として/③イメージとして捉えるという三分法に則るならば、まず、個人としての「メンヘラ」という切り口からは、壮絶な人生や生々しい感情が綴られた、日記や自伝的文章を批評対象にすることができるように思います。例えば、ちくま新書の『友だち地獄』(土井隆義)において、『二十歳の原点』の高野悦子と『卒業式まで死にません』の南条あやが比較されています。時代は30年異なるものの、自傷癖があり、文才に優れ、若くして自殺したなどの共通点があったために比較されたのでしょう。この二人は「メンヘラ系」に含まれるのではないかと僕は思います。
実際、Twitterにおける「メンヘラ界隈」において南条あやの名前を聞くことは多いですし、南条あやへの「憧れ」が語られるのを聞いたこともあります。親との葛藤やリストカットやオーバードーズなどの体験を含む日記をインターネット上に投稿していた南条あやは「メンヘラ」にとっての一つのモデルとなっていると言えるでしょう。その証拠、と言えるのかは分かりませんがGoogle検索をしていたらこんな記事も出てきました。
一般的に言えば、「自分語り」的な日記や自伝のような文章は、その壮絶な人生や生々しい感情を表現しやすいことなどが理由で「メンヘラ系」というジャンルに含まれることがあると言ってもいいと思います。最近でも例えば、小野美由紀さんの『傷口から人生。 メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』という自伝的エッセイがありますが、これは「メンヘラ系」というジャンルが存在することが意識されたタイトルだと思います(とはいえ、小野美由紀さんが「メンヘラ」というカテゴリーに含まれるかどうかはまた別の話です)。
歌手にも「メンヘラ系」は存在すると思います。パッと思いつくので言えば、Cocco、椎名林檎、大森靖子あたりでしょうか。これらの歌手においても、生々しく衝動的な感情を表現している側面などに「メンヘラ系」らしさがあるように思います。他にも、ミオヤマザキやアーバンギャルドあたりもジャンルとしての「メンヘラ系」を自覚的に使いこなしている例だと思いますし、ビジュアル系の一部は「メンヘラ系」と重なる部分があると思います。僕には知識がないので詳しくは分かりませんが、歴史的に言えばゴスgothカルチャーから「メンヘラ系」への連続性が見られるように思われます。そこでは「死」をイメージさせるある種の耽美なものが「メンヘラ系」と結びついているのでしょう。
挙げだすとキリがないので割愛しますが、映画や小説などにも「メンヘラ系」というジャンルは存在するでしょう。この場合も、物語の登場人物について個人としての「メンヘラ」という切り口から考察することができるでしょうが、それでは関係としての「メンヘラ」についてはどうでしょうか。
2でも既に述べましたが、「毒親(家族)」や「虐待」や「DV」や「共依存」、「いじめ」、「ブラック企業」などの閉鎖的・権力的・暴力的な関係性は「メンヘラ系」と関連が強いと思われます。これらの関係性が含まれる作品等がただちに「メンヘラ系」というジャンルに分類されるとまでは言えないでしょうが、先ほどの個人としての「メンヘラ」と同時に登場することもそれなりにあることでしょう。例えば、ドラマにもなった『君が心に棲みついた』(天堂きりん)という漫画では、上司の男性が主人公に対してモラルハラスメント的な接し方をするのですが、それと同時に主人公個人のネガティヴな性格などが描かれます。同じく漫画で言えば『君に愛されて痛かった』(知るかバカうどん)は、作品全体のトーンとして「メンヘラ系」に分類してよいと思われますが、この作品でも学校でのいじめが重要な位置を占めています。
そして、ここまで述べてきた「メンヘラ系」というジャンルはやはり「イメージ」の産物です。「メンヘラ」というカテゴリーを用いることや「メンヘラ系」というジャンルの存在を受け入れてそれに乗っかることは、人々のコミュニケーションや様々なメディアを通して再生産されていく「メンヘラ」のイメージに踊らされて、「メンヘラ」のスティグマ化に加担してしまっているのだという批判があるかもしれません。例えば、「いざとなれば自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていける」ということを標榜した『完全自殺マニュアル』(鶴見済)が、実際には自殺を誘発する「有害図書」であるという見方も否定はしきれません。先ほど挙げた南条あやの「マネをする」人が現れたことについて、テレビやゲームにおける暴力シーンへの規制と同様の論理で「有害」だと批判する人もいるでしょう。
このような批判にはどのように応答することができるでしょうか。このことについて「メンヘラ批評」が持つ意義も含めて、述べたいと思います。
5.「メンヘラ批評」の意義
資源としての「メンヘラ」という言葉
まず、現に「メンヘラ」というカテゴリーのおかげで人との繋がりができたり、自分自身の生きづらさについてより深く知るキッカケを得られたりした人もいることでしょう。逆に、「メンヘラ」というカテゴリーがスティグマとして働いて人々を傷つけたり、むしろ歪んだ形で自分自身を見てしまったり、ピエロのように自分自身をコンテンツ化することで危険な行動が際限なくエスカレートしてしまったりという人もいるでしょう。これらにおいて問われるべきなのは「『メンヘラ』というカテゴリーを用いたり、『メンヘラ系』というイメージに乗っかったりする際に、メリットとデメリットを比較してどちらが大きいと言えるのか」ということになるでしょう。
これは簡単に答えの出せる問題でありませんが、僕の考えを述べます。現に「メンヘラ」というカテゴリーが、自分自身のアイデンティティや世界の見方において、必要不可欠なものになっている人はいると思います。そういう人に対して「メンヘラという言葉を使わずに、別の言葉を使いましょう」というのは酷なことではないでしょうか。むしろ、その人にとって納得のいく生き方や世界の見方を得てもらうためには、まずその人が持っている「メンヘラ」という概念に寄り添う必要があると思います。既にその人は「メンヘラ」の概念を持っており、手放すことは難しい状態にあるのですから、だったらひとまず「メンヘラ」から出発するべきです。そうして、納得がいくところまで少しずつ自身のアイデンティティや世界の見方をズラしていく、そちらの方が誠実なやり方なのではないかと僕は思います。
このことは「当事者研究」の考え方から述べることもできます。「当事者研究」とは統合失調症などの当事者が、自己病名をつけて症状を分析したり、そこから生じてくる生きづらさや固有の経験を自分たちで研究したり、発表したりするという活動です。これは、「べてるの家」という北海道にある精神障害者を中心とした地域コミュニティで発明されました。べてるの家では幻覚や妄想をむやみに否定せず、互いに発表し合う「幻覚・妄想大会」というものが行われています。ここで重要なのは、病院で患者の状態を医者が診断し治療するというモデルを超えて、自分たちの状態を自分たちで解釈し、どうしていくかも自分たちで考えていく当事者の自己決定が重視されているということです。更に、医学的に見てもこういった活動は統合失調症に対して治療的介入として用いられるオープン・ダイアローグと類似しており、治療的効果があるとも考えられます。
「メンヘラ」という言葉もまた、医学的な病名だけでは自分自身のことを捉えきれない人にとっての一種の資源としての言葉になれば良いなと思います。「メンヘラ」という言葉は誰かにレッテルを貼って終わりの「出口」の言葉として使われるべきではありません。自分自身の生きづらさについて研究するためのキッカケ、つまりは「入口」として価値があるのだと思います。
ということで、「メンヘラ批評」が「メンヘラ」にまつわる様々な見方を打ち出すことを通じて、読者の方が自分自身のことを見つめるキッカケを得られれば、と思います。
いくつかの注意事項
とはいえ、もちろん精神医療や心理療法を否定しているわけではありません。むしろ、病院に通い、自分の状態をはっきり伝え、用法容量や指示をちゃんと守るということが治療や生活においては大前提として重要であるということは強調しておきます。過度の権威主義にも問題はありますが、やはり、長年の研究が蓄積されている医療の力には頼るべきです。また、日常生活においても医学的な病名を用いるべきではないと言っているわけではありません。
大事なことは、「メンヘラ」という言葉も病名もあくまで、一人の人間にとっては部分的なアイデンティティでしかないということです。当然、人間の精神状態や思考パターン、性格、行動、対人関係、能力などといったものがすべて「メンヘラ」や病名で説明できるわけではありません。できることは、自分自身がどういう人間であるのか、生きるためにどういう戦略を用いることができるのかといった認識を部分的に深めることだと思います。そのために、そのようなアイデンティティの断片を拾い集めることが役に立つ場合があるでしょう。「メンヘラ」という言葉はあくまで数ある資源の一つであると僕は考えています。
「メンヘラ批評」が「メンヘラ」のエンパワメントを標榜していることは冒頭で述べました。その上で、最も分かりやすい「メンヘラ批評」の意義は「メンヘラ」という言葉を資源として豊かなものにすること、これだと思います。
ただし、そもそも「メンヘラ」という言葉のせいで傷ついており、「メンヘラ」という言葉が存在してほしくないのだという人もいると思います。確かに、「メンヘラ」という言葉がネガティブなイメージのまま、3で述べたようにある種のスティグマとして用いられている内は、「メンヘラ」という概念が広まれば広まるほどデメリットがあるでしょう。
しかし、「メンヘラ」概念が資源として用いられ、一定の市民権を得ていけば、「メンヘラ」という言葉のイメージの改善にも繋がるでしょう。すると、「メンヘラ」概念のせいで傷ついてきた、「メンヘラ」という言葉が嫌いだ、という人たちに対しても、長期的に見ればメリットをもたらす可能性があるということになります。僕自身の意見としては、現に「メンヘラ」という言葉は社会において使われており、差別用語として強い規制がなされているわけでもないというところから、「根絶」することは難しいと思います。そこで、むしろ発想を逆転させて、「メンヘラ」概念の「良い用法」を普及させていくべきだと思います。それは先ほども述べたように、短絡的な形で自分や他人にレッテルを貼るために「メンヘラ」という言葉を用いるのではなく、考えるための出発点、資源として「メンヘラ」という言葉を用いていくことだと思います。
ただし、もう一つ大事なことを付け加えておきます。「メンヘラ批評」は「メンヘラ」という言葉を軸につながりやコミュニティを作ることを志向しているわけではありません。そのようなつながりやコミュニティは孤独の解消に寄与するという面では良いこともある反面、人間関係のトラブルや、健康上のリスクがある行為の伝染・エスカレートに繋がる可能性があります。個人的にはそういうコミュニティにおいては、ある程度支援者的な立場の人間がいたり、相互扶助的な文化が浸透していたり、リスクを回避するためのポリシーやルールがあったり、ということが重要だと思いますが、「メンヘラ批評」にはその用意はありません。
6.「メンヘラ」という言葉を資源として用いた実践例
「メンヘラ」という言葉を資源として用いる、ということを具体的に想像できない人もいるかと思いますので、活動の例を紹介しておきましょう。まず、2014~2017年頃に複数回行われた「メンヘラ展」というグループ展では、「メンヘラであること」を結集軸にして様々なアーティストが出典しました。これは「メンヘラ」としての表現の可能性を広げた一つの出来事だったと思います。僕自身も「メンヘラ展2」にお邪魔したことがあり、その感想記事が残っています。
4年半も前の記事なので稚拙で恥ずかしいですが、記事を読み返すと、「『メンヘラ』という言葉に内在している多様性を、そのまま多様に表現する」ということを僕は当時評価していたようです。これは「メンヘラ」という言葉を切り口にする「メンヘラ批評」においても見習いたい視点です。
また、現在も活動が続いているメンヘラ.jpというサイトは「メンヘラ」を「メンタルヘルスに問題を抱える当事者」と一般的に定義した上で、自己表現、承認、情報提供の場を作っているという点で意義があります。このサイトもまた、「メンヘラ」という言葉を用いているからこそ届く層がいるのだと思います。おそらくこのように「メンヘラ」の定義を一般的にすることで、「メンヘラ」という存在を特殊なものにするのではなく、「みんなつらいんだから、そんなに頑張らなくていい、そのままでいい」というようなメッセージを伝えているのだろうなと思います。メンヘラ.jpについては批判も含めて紹介した記事を書いていますので、詳しくはそちらを参照いただけると幸いです。
7.ホリィ・センはなぜ「メンヘラ批評」をやるのか
最後に、僕自身の立場を踏まえた上で、なぜ「メンヘラ批評」プロジェクトを立ち上げたのかを述べておきたいと思います。
僕自身は基本的には自分のことを「メンヘラ」だとは思いません。せいぜい、たまに精神が不安定になったときに自分自身をメンヘラ的な状態になっていると思う程度です。にもかかわらず、「メンヘラ」という言葉にこだわり続けているのにはいろいろ理由があります。
わかりやすい話で言えば、僕は3年前、「メンヘラを好きな理由」を書き出してみたことがあります。ツイートが残っているので貼っておきます。
メンヘラが好きな理由、まじめにまとめるとこのあたりだと思う。こうしてまとめるとダメなところもいっぱいあるなあ pic.twitter.com/z0VxCjsTii
— ホリィ・セン(サークルクラッシュに詳しい人) (@holysen) January 25, 2016
このときから既に、自己批判を込めて露悪的な書き方をしていたように思いますが、今ももしかしたらこういった気持ちが無意識下にはあるかもしれません(意識の上ではもはや「庇護欲」のようなものはありませんし、「普通」からズレた自分を受け入れてほしいというような気持ちもありません)。いずれにせよ、「メンヘラ」的な人の助けになりたいという気持ちは未だに普通にありますし、自分のことを「メサイア(救世主)コンプレックス」だと言うこともあります。
そのような気持ちを持つようになったキッカケまではもはや思い出せませんが、自分の中ではメンヘラ神という人との関わりが大きかったと感じています(メンヘラ神とのことについてはこの記事に書きました)。
その後も、様々な生きづらい系の人と関わってきました。自分とのやりとりが助けになったのかどうかは正直あまり分かりませんが、自分なりにできることをやろうとずっと考えてきました。今でも個人的に相談を受けたり、コミュニティを運営したりといったことは(全盛期ほど精力的ではありませんが)続けています。最近では、「メンヘラ当事者研究会関西」の活動もやっていきたいと考えています(忙しい時期もあったために、長らく開催できていないのが心苦しいですが、本当は月1ぐらいで開きたいものです)。
しかし、自分の中の変化として、大学院生としてもう4年間過ごしたというのが大きく効いています。数年前に比べて圧倒的に読書量も増え、「僕はアカデミズムの人間に(研究者に)なりつつあるんだ」という感覚が急速に芽生えてきました。
そんな中で、文章を書くことの意味合いも変わってきたように思います。僕はサークルクラッシュ同好会での活動を通じて、「自分語り」を繰り返してきました。「何周まわったんだろう、もはや語り尽くしたな」という感覚があります(と言いながら、今まさに自分語りをしているのですが……)。そこで、自分のためではなく、社会のために言葉を紡ぎたい、という気持ちが湧いています(そんなこと言うんなら論文を書けよというツッコミは措いておきます)。
また、僕は「メンヘラ」という言葉を“うまく”使えないかということを長らく考えてきましたし、「メンヘラ」なるものに対して異様な情熱を傾けてきました。「この情熱をどうにか有効活用できないか」と考えるわけです。そんな中で、メンヘラ.jpのような実践的な活動には正直少し憧れました。
社会のために言葉を紡ぎたい、「メンヘラ」への情熱を有効活用したい、それらの思いがどういうわけか混ざり合い、このたび「メンヘラ批評」に結実しちまったわけです。コンセプトに賛同していただける書き手を、そして、新たな世界を切り開きたい読者を、お待ちしております。よろしくお願いします。