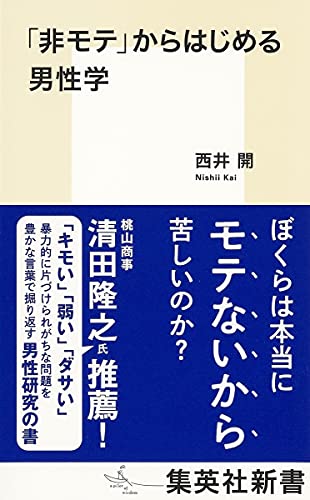ホリィ・センです。友人の小峰ひずみhttps://twitter.com/cococooperativ1/が『臨(サイド)』という批評誌(?)を出したので、宣伝します。
僕はサクラ荘というシェアハウスをやっていることから小峰くんからインタビューを受け、「シェアハウス思想探訪」という物々しいタイトルの記事があります。
『臨(サイド)』から一つ記事を載せてほしいとのことだったので、僕は小峰くんの書いた「オナニーから疑え――〈男らしさ〉と快感――」という記事を転載します。笑えるながら、かなり真面目な記事です。
『臨(サイド)』の目次:
〇思考にとって「現場」とはなにか?――臨床哲学・再論――(小峰ひずみ)
〇中毒政治論――依存・ケア・回復・闘争――(小峰ひずみ)
〇二十一世紀の支援と代弁――現場から〈イタコ〉へ――(田中俊英)
〇少子化時代のフェミニズム――子育て VS 資本主義――(九照)
〇人間のカテゴリーと〈私〉の関係(ひかるころも)
〇オナニーから疑え――〈男らしさ〉と快感――(小峰ひずみ)
〇シェアハウス思想探訪――サクラ荘主宰に話を聴く――
-----
オナニーから疑え―〈男らしさ〉と快感―
小峰ひずみ
―そういえば、オナニーする男の姿や表情は、仏像によく似ている。
右掌に輪をつくり左でほとばしりを受けるような形ではないかね?
野坂昭如
オナニーから疑え
私の人生はセックスするよりも、オナニーする回数のほうが多いのではないか。そう気づいたとき、なにかとんでもないことに気づいてしまった気がした。男の悩みの半分はセックスである。断言していい。みなセックスで困っている。私も困っている。
かの有名なAV監督・二村ヒトシは言う。
「モテないこと以外のほとんどすべての不幸は、モテてさえいれば、なんとかなる(か、ガマンできる)」[1]。
しかし、我々の実際は次のようなものではないか。
夜になる。さあ、待ってましたとばかりにベッドに潜り込めど、セックスが下手なら相方は眠り込み、腹いせにソープに行ってもケチればそれ相応のサービス、女は男をバカにするか、身勝手に怒ってミソジニー(女性嫌悪)の闇にはまり八つ当たれば、呆れられて、見捨てられて、そもそもセックスする相手がいなくなっている。
しかも、セックスせずんば人にあらず、セックスこそ人生最大の至福との俗説、天馬のごとく七つの海を駆けめぐり、わが宿、半地下の安宿にして、上階より三日に一度ほど夜中、パンポコ聞こえてくるような薄壁であってみれば、セックスばかりが関心ごとになっても咎められる筋合いはない。
しかし、もし、その「セックス」とやら、実は私のからだにとってはたいしたことのないものだとしたら、どうだろうか。というよりも、もっと大事なことがあったとすれば。それは私が人生を歩んでいくうえで抱える悩み、あるいは問いをまちがっていた、ということになる。
セックスばかりを問題とすること、させられること、それは言ってしまえば、生まれたときからともに時を歩んだ我が愚息を、他人(セックス商人どもの)の価値観にゆだねていた、ということになりはしないか。まるで敵国に人質として預けられ幼き頃から委縮していた竹千代(のちの徳川家康)のごとく、ちんぽこを委縮させていたということになる。
どうりで立たないわけである……。
ならば、全国のオナニーを愛す、いや、もう愛するとかではなくて、やっちまう人々よ、我と汝の愚息のために、精神において立ち上がり、身体においては各々、好きな姿勢を取れ。
オナニーから疑ってかかれ。
感じる男―男オナニーひとり道―
「オナニーをすると女になる」と誰かが言っていたが、たしかに、「快楽を感じるのは女の役割」との意識、男にはこびりついているのではないか。私にはある。
大学生の頃だったか、ベッド上で射精が終わったあとに、隣にいたセックス・パートナーから顔をまじまじと見られ、一言「かわいい」と言われて、イラッというか、ムカッというか、少なくとも喜ばなかったという記憶があるのだ。
感じるのは女、感じさせるのは男。男が感じるなど、恥ずかしい。理不尽な性的分業、ここにあらわる。だとすれば、フェミニストが嫌い、男性学が脱しようとする、〈男らしさ〉なる呪縛からの解放、まずは「感じる」ところから始まる道があってもよい。
この世には「男は不感症である」との説がわりと一般的にある。『火垂るの墓』で有名な野坂昭如は『エロトピア』のどこかで「男の快感は女の七十分の一」ほどだと言っていたはずだし、「草食系男子」という言葉の火付け役である生命学者の森岡正博は「男の不感症」を主題的に論じている。森岡は次のように言う。
「どんなに努力してみても、射精の直後の、あの興奮がすーっと醒めていく空虚な感じだけは決してなくならない…[後略]…。「死をイメージさせる虚無感」という渡辺[淳一―筆者]の表現は的確だ。射精がいつもこのような絶望的な感覚で締めくくられてしまうこと、これこそが「男の不感症」の核心なのである」[2]
私もそう思う。私もまた、セックスにせよオナニーにせよ、射精が終わったあとはもうどうでもいいやという投げやりな気分になり、虚しさに覆われる。キモチいい、か? 決して「人生最大の至福」が終わったあととは思えない。不感症である。
さて、森岡は「男の不感症」を脱するために二つの道を示している。
ひとつは、「不感症がいやなら、真の快楽を感じることのできるようなセックスを学べばよい」[3]という主張。感じればいいじゃん、ということだ。単純明快、わかりやすい、説明不要のことと思う。性的技術派である。
もうひとつは、不感症であることを堂々と認めることで、「生命あるもの、傷つきやすいものに対する「やさしさ」へと振り向けていくこと」[4]が大事だという主張である。しかし、この主張は、正直、よくわからない。具体的な説明がない。「マスターベーションした直後に、人々に対するやさしい気持ちを自分の心の中に満たしてみるといいかもしれない」[5]と言われるのだが、What?!って感じである。さっぱりわからん。まあ、どうやら、「やさしい」イメージ、草食系男子へ至るイメージだ。
森岡は前者=技術派をやんわりと排撃し、後者の道を選びたいという。では、森岡はなにゆえ快楽追求の技術派をやんわり否定するのか。彼は言う。
「私は彼らの試みを否定しない。しかしながら、私は、彼らとは別の道を進もうと思うのである。なぜなら、彼らのように真のオーガニズムを追求する方向に行ってしまうと、自分のセクシュアリティのねじれや、対人関係のねじれを維持したまま、「性の快楽への欲望」だけが肥大することになりかねないからである」[6]
なるほど、わからなくはない。
「具体的に言えば、極上のオーガニズムを得るために、プロの売春婦相手のセックスを繰り返すような男が出来上がっても、まったく仕方がないからである」[7]
至極、もっともである。
しかし、残念ながら、私たちはその「極上のオーガニズム」とやらを味わうための時間も金もない。私たちにとって、射精は(ものすごく、という意味でも、一瞬は非日常的快楽を得る、という意味でも)「超」日常的な実践である。
虚しい射精か、「極上のオーガニズム」か、という選択肢しかないのだろうか。だとすれば、男とはたしかに不幸な性だと言えるだろう。
しかし、諸君、はじめてオナニーと出会った日のことを、まるで初恋の人を思い浮かべるがごとく、思い出してみよ。テーブルに我が逸物を押し付けて快感に目覚め、おそるおそる三本の指でしごき、ついには小遣いをはたき親の目をはばかってTENGA(オナニーホール)にまで手を出しながら追求してきた、その道、私たちはオナニーと共に精神的発達を遂げてきたのではなかったか。私たちがその先端から宙(そら)へと我が白濁の魂を噴出するのは、決して「極上のオーガニズム」のためではない。日常の一部なのだ。つまり、ごはんなのだ。
大見えを切って、もう少し言えば、オナニーとは「おひとりさま」という単身者が多くなった現代社会で、その単身者が性的生活を送るための最後の砦である。若き頃なら当然だが、性欲なるもの齢九十まで続くと言う。人は老いれば、無我の境地にいたれるわけでもないらしく、ただ、ひとりでシコシコするしかないのだ。とすれば、『男おひとりさま道』(上野千鶴子)、それは必然的に「男オナニーひとり道」であるよりほかない。
老いてもシコシコ。
この冷酷な事実を想起し、夜中に布団で打ち震える男子の数、統計は取れねども、あまたいると確信する。(安心しろ、私は君らの仲間だ。)
オナニー、それはひとりで生きると決めた男の覚悟なのだ。
という悲壮な心持ちを抱きつつ、私は『男のオナニー教本』なるものをAmazonで買ったのである。
さて、お待たせした。
いよいよ、実践編である。
自己への前戯
さて、みなさんはいったいどのような姿勢でオナニーをされるか。
あぐらをかいてか。
寝そべってM字開脚か。
まさか足をピンと伸ばしてオナニーしているのではあるまいな?
私はまさしく足ピンオナニーを十数年愛好してきた人間のひとりである。
足ピンオナニーをしていると、筋肉が緊張してか、たしかそんな理由で(曖昧)、すぐに射精することができる。時間のない現代人にとっては都合のいい姿勢だと言えよう。しかし、その快感たるや、まさにしょんべん、あるいはそれ以下、我慢に我慢を重ねたうえでの御排尿のほうがよっぽど気持ちよい。これでは、男が「不感症」なのも当然と言える。
そもそも、私の場合は、オナニーを右手でするものと思っていた。しかし、AV女優のオナニー動画を見ると、どうも右手でチツ、左手でムネ、武蔵流の両刀使いである。他方、私などは右手でサオ、左手はスマホ、北辰一刀流と言えば聞こえはいいが、なに、ポルノの刺激で快楽物質を無理に出し、足ピン状態でサオをしごけば、野坂の言うところの「二こすり半」、すぐに我が魂も顔を見せ、天に昇る意志もむなしく、スマホから素早く持ち替えたティッシュペーパーにぴしゃりと落ちる。これでは、快楽もへったくれもない。誰だ、こんな身体につくりあげたのは? とアッラー、ヤハウェ、イザナミに怒ってみても仕方がない。
しかし、実践性科学研究会著・『男のオナニー教本』には次のように書いてある。
「[オナニーに必要な―筆者]時間は、一、二時間」[8]
一、二時間?!
「二こすり半」が、「一、二時間」?!
いや、たしかに、ポルノ動画を探していたら、一時間すぎていたこと、ままある。だが、オナニーに一時間、ましてや二時間、聞いたことがない。
これ、どういうことか。
端的に言えば、前戯をするかどうかの違いである。
まず、この本では前戯として、我が愚息の下方に鎮座しておる「玉」様をなでるところから始まるのだ。ついで、サオの裏をやさしく撫でる。オナニーの本番がサオのしごきだとすれば、タマをもむのは愛撫と言えよう。
そうすると、当然ながら、右手にサオ、左手はタマとなるわけだから、両刀使い、ポルノは使えない。かといって、女体を想像しろとは言わないのが、この教本のよいところ、「頭の中でどんなことを考えても自由」[9]とおっしゃる。ならば、と、私は勃起し本番が始まるまで、右手で金玉をもみ、左手で大塚英志という批評家の評論を読んでいたが、ま、立たなかったね。
大塚英志はそれくらいおもしろいのだ。
男はオナニーと共に生き、感じ、精神的発達を遂げる存在であること、これ、私の持論であるが、男性学という〈男〉について論じる学問もついぞオナニーを論じぬ(私の知っている範囲では)。先ほどより引用している森岡正博の『感じない男』はオナニーについて考えた珍しい考察であるが、それ以外はなぜか女が男の身体について論じている。
金田淳子という社会学者と澁谷知美という社会学者の「新たなる男性身体の〈開発〉のために」という勇ましき対談は男が読んでもかなりおもしろい。そのなかで、金田は次のように言う。
「男性が自らの身体性と向き合う困難という点に関連して私が常に思っているのは、男性がもっと自分の身体に対して肯定的になれないものかということなんです。よく、男性の多くは自分の身体を汚いと感じているということが言われますが、これだけジェンダーギャップ指数の低さが指摘されるなか、それでも女のほうが恵まれていると頑なに言い張る男性が絶えない最大の原因は、男性たち自身の男体嫌悪ではないか。」[10]
私は一読、むかついて、この文章の上に「×(バツ)」をつけた。私の考えでは、女のほうが恵まれていると男が感じるのは、女は年収が低くても結婚して「主婦」という役割を得ることができるのに対し、男は年収が低いと結婚さえしにくい(している人はたくさんいるが)という「負けっぷり」の非対称性に起因していると考えている(し、この二人もそれは知っている)が、そんな冷酷な現実はここではどうでもよい。
しかし、私がこの引用にむかついたのは、私と金田の認識の違いだけではあるまい。おそらく、この引用が問題の奥深くをえぐり出していたからではないか。
男の体とはなにか? 特にその象徴と考えられているペニスとは?
澁谷はペニスを「〈強くて、硬くて、頑丈な〉男性身体の象徴」[11]としているが、残念ながら、我が愚息、そのようなものではない。「血は立ったまま眠っている」(寺山修司)、その具体的現実である勃起せるちんぽこを手の平を大きく開いてさわってみるべし。その下方には、あのやわらかき玉袋がある。
そこは男性の急所、コメディ・ドラマでは女にけり上げられる場所だ。
日本を代表する大作家・村上春樹は金玉を蹴り上げる練習をするボディ・インストラクターを物語に登場させている。彼女がある男に「睾丸を思いきり蹴り上げられる痛さがどのようなものか」と尋ねたとき、その男は熟考し、こういった。
「あれは、じきに世界が終わるんじゃないかというような痛みだ。ほかにうまくたとえようがない。ただの痛みとは違う」[12]
私はこの一節をみたとき、この作家は男にとっての天災だなと思った。誤字ではない。続いて、私たちが読むべきは他の作家ではなく、『男のオナニー教本』である。
「陰のうの中の睾丸の形を一個一個確かめたり、軽く転がすように握ったり離したり、手のひらで円を描くようにさすったりして、じっくりと時間をかけて刺激しましょう」[13]
金玉、そこは男の急所であり、痛みと快楽をもたらす箇所である。なにより、ぷにゅぷにゅとやわらかい。金玉はそのやわらかさゆえに、他者の手を、そして、自己の手を受け容れる場所である。
さっそくさわってみよう。
……あな、やわらかきこと……、
……はあぁ……。
この自己への前戯の手ざわりを私たちはよく覚えておかねばならない。それは自分の最もデリケートな部分、〈傷つきやすい(ヴァルネラブル)〉部分である。そして、その傷つきやすさゆえに、苦しみと歓び、痛みと快楽を併せもつ。この〈傷つきやすさ〉を認められないことこそ、つまり、そそり立つペニス中心主義とやわらかき金玉の否認こそ、男の呪縛ではないのか。
「男たちの最大の罪(自己欺瞞)とは、まさに自らの痛みに気づけないこと、「痛い」や「苦しい」と口に出せないことかもしれない」[14]
杉田俊介という批評家は「男たちは、なぜ、「助けて」と言えないのか」との疑問にこう語る。「痛い」「苦しい」と言えないこと、それが男たちの最大の自己欺瞞だ、と。男は「痛い」や「苦しい」と言えない。それは同時に、「感じる」「気持ちいい」と言えないことではないのか。感じるのは女の役目、感じさせるのが男の役目。その呪縛は、男の最大の自己欺瞞につながっているように思う。
やわらかきこと、それを男は意識としても、身体としても忘れているとは言えないか。
女にけりあげられる急所、その急所こそ、痛みと快楽を感じる〈傷つきやすさ〉の結集点である。愚息はそそり立つも、金玉はやわらかい。そのような〈傷つきやすいちんぽこ〉という認識からしか、男は「痛い」「苦しい」と言えないだろうし、また、自らの傷を「手当て」し「ケア」(杉田)することもできないだろう。そして、「手当て」に値しないものを愛せるはずもなく、男体嫌悪はつのっていく。
オナニーが重要なのは、ペニスに象徴される男の体が前戯を必要とし、それゆえに、「手当て」を必要とするものとして認識をできる日常的な行為だからだ。人は毎日、男性学の本を読んでいるわけではない。しかし、オナニーは一日一回、二日に一っぺん、少なくとも三日に一度はする。だとすれば、男性学の百冊はオナニーのいっぺんに如かず、とも言えそうだ。
杉田は言う。
「ラディカルとは、急進的というよりも、根源的であろうとすることだ。それは日常や生活にも根を張らねば力が足りないものになってしまう」[15]
私もまた、「ラディカル(根源的)」でありたいと願う者である。
私たちは「ティッシュなし」でオナニーができる
もう少し男体嫌悪を掘り下げよう。
森岡はある男性が「男の体は汚い」と聞いて、「その通りだ」と実感した、という。では、その汚い男の体とは?
「体毛が密集し、肌の色は悪く、骨がごつごつしており、筋肉がうっとうしいこの体。精液によって汚れてしまうペニスと周辺の毛。自分の体はほんとうに汚いという実感がある」[16]
わかる。特に、射精がやっかいだろう。森岡もできるだけ射精しないようにオナ禁していた学生時代があったと告白している。杉田が引用するデータによれば、中高生のときに、射精を「汚らわしい」と感じる男性は約一八%にものぼったという[17]。
だが、私の予想では、もっといる。
でなければ、ティッシュを持ってオナニーすること自体がおかしい。射精が汚くないのであれば、単に自分の体にその「魂」をぶちかまし、その後にティッシュでふいて、風呂に入ればいいだけの話だ。
しかし、いままで頼りにしてきた、かのオナニー教本でさえ、「ティッシュペーパーを横に置いたら、一切の余計なことは考えず、力を抜いて仰向けになりましょう」[18]とティッシュを推奨しているのである。しかし、私の経験では、精液は体にぶちまけたほうが気持ちいいのである。いったい、実践性科学研究会の面々はなにに遠慮しているのだ?
やはりここには、オナニー・オブ・ジェダイたちさえも戸惑わせたビッグ・フォースが潜んでいると考えてよい。
だとすれば、ここは、日本文学史に残るオナニー・マスターに登場していただこう。野坂昭如はオナニーをする男の姿についてこういう。
「そういえば、オナニーする男の姿や表情は、仏像によく似ている。右掌に輪をつくり左でほとばしりを受けるような形ではないかね?」[19]
これを一読して、私は「え?」と思った。
ティッシュペーパーの記述がない。
ティッシュペーパーの存在が、ここでは自明ではないのだ。
左手でじかに「ほとばしりを受ける」のか?
野坂、やりおる。
もちろん、ここに記述されていないだけで、ほんとうは傍にティッシュがあるのかもしれない(きっとあるだろう)。
しかし、ここで野坂が書き漏らしたことで得られる想像力は、私たちのオナニーからひとつの幻想を取り払ってくれるのではないか。
すなわち、私たちはオナニーができる、ティッシュなしで。
しかも、先ほども述べたように、私の実感ではそちらのほうが、解放感があってよろしい。よろしい、というか、キモチがいい。ティッシュを切らしたもののたまりにたまって仕方なく自慰にふけったことのある人々も、実は「こっちのほうが気持ちいいのでは?」と思った人がいるのではないか。
では、なぜ、ティッシュなしでシコらないのか。精液が汚いからか。しかし、精液は我らが白濁の魂である(と、とらえることもできる)。
ティッシュなしでオナニーする日があってもよい。精液を身近に感じる日があってもいい。
そのようなラディカルな(日常的な)実践が徐々に私(たち)の男体嫌悪を溶かしてくれるような気もする。
もちろん、これはひとつの仮説、可能性にすぎないが。
フェミニストの旗手・上野千鶴子といえば、泣く子も黙る言論界の覇者であるが、彼女はご存知の通り、わりと男に手厳しい。どこかの対談で「男は女に依存している。そのことがわかっているから、逆にミソジニー(女性嫌悪)に陥る」と述べていたはずだ。まさに、男は己の精神的玉袋をけりあげられた格好になったわけであるが、その痛み、しかと体に刻むべし。男は女に依存している、こんなことはフェミニズムの洗礼を受けた若い世代の女性は、とっくに気づいているだろう。
さて、手元に上野の対談集がないので、どのような意味で彼女が「男は女に依存している」と言ったのかはわからないが、私の経験を照らしてもだいたいの予想はつく。
第一に、性的依存。すなわち、セックスする相手として依存している。
第二に、インチキ自己肯定(「彼女いる・モテる俺」)を保つための依存。
第三に、女にモテたから自分の汚い体を肯定できるという依存。
昔であれば、お見合い結婚という形なので双方「男」「(子どもが産める)女」であればよく、付き合う期間もないまま、すぐに永年連れ添うことになるので、幸せかどうかはともかく、話は簡単なのであるが、いまや恋愛結婚全盛期をとうに経た時代、男も女も「私自身を愛して」という実存を賭けてマッチングアプリや盛り場に繰り出してくるものだから、ややこしい。男は「女」なるカテゴリーを必要とし、女は、これ、どうか知らない。きっと「男」なしで生きて行くだろう。
金田と澁谷は「女と付き合うならコミュ力をつけないといけない」という上野の発言に激怒した男たちについて、次のように言う。
「たしかに「なぜ女がケアしてくれないんだ」という不満がありそうですね。とはいえフェミニズムは、恋愛や孤独の問題にかんして「男たちよ、もっとモテない女と付き合え」などとは言わず、自分たち自身でやってきたわけだから。」(金田)
「そうなんですよ。私もそれはふつうだと思ってきたのですが、それができないのはやはりなんとしても女とつがいたいという欲望があるからだろうと私は踏んでいます。本来であれば男性たち自身が、恋人や配偶者のいない男性を肯定する営みをどんどんしていくべきなのに、なぜかしようとしない」(澁谷)[20]
この男女の違い、男にとっては由々しき差異である。しかも、男にとってより都合が悪いのは、このような依存構造を女は肌感覚で気づいていて、依存すればするほど、逆にモテない、ということだ。求めれば求めるほど、離れていく……。
では、この依存からどのように抜け出せばよいか? とにかく、第二と第三の依存からは独力でも抜け出せるのではないか? これはしばしば「モテ論」として語られてきたことだ。
先ほども引用したAV監督の二村ヒトシは「自分の【居場所】をつくる」のが大事だとしたうえで、次のように言う。
「【あなたの居場所】というのは、チンケな同類がうじゃうじゃ群れてるところじゃなくて【あなたが、一人っきりでいても淋しくない場所】っていうことです」[21]
あるいは、『草食系男子の恋愛学』で森岡正博は次のように言う。
「真の自信とは、他人との比較をやめたあとに生まれる控えめな自足のことである。このような心境に近づいたとき、…[中略]…「人間として成長したいと思っていたり、将来に対して夢を持っていたりして、全身からまっすぐに立ち上がる心意気があふれている」という若い男の人間的な魅力が、はっきりと備わり始める」[22]
とのこと。両者の共通点は「一人っきりでいても淋しくない場所」「他人との比較をやめたあとに生まれる控えめな自足」にあるといっていい。つまり、一人でもOKということだ。
これはオナニーにも言えるのではないか? つまり、オナニーを「一人でいても淋しくない」場所にできたら、私たちはどんなにか救われるだろう。
金田と澁谷は男がミソジニーに陥るのは男による「男体嫌悪」の原因があると述べていたが、「女にモテたから肯定できたという迂回路をとらず、自分で自分の身体を肯定してほしい」という。「[自分の体を自分で愛することで]自己完結して、これ以上女を迫害するのをやめてほしい」とも言う。
男が女に性的に依存し、自らの身体の肯定も女に依存しているのであれば、そこから脱するために、オナニーはどのように変われるか?
この命題の検証は、われらのオナニー・チャレンジにかかっていると言っても、過言ではない。
挿入れない関係―男と女のレズビアン・セックス―
子よりも親が大事と思いたい。セクよりオナが大事と思いたい。そう思って、しばらく論考を進めてきた。しかし、ここでセックスについて論じないのもどうかと思う。というのも、人間はたまには(しばしば)セックスをするからだ。そこで単なるオナニー野郎になってしまっては、つまらない。ここは裏切り者の罵声、全身で浴びることを厭わず、セックスについても論じたいと思う。
芥川賞作家・村田沙耶香は『消滅世界』でジェンダーレス社会を描いている。その社会は女が「男」になる社会ではなく、男が「おかあさん」になる社会だ。夫婦間のセックスが禁じられ、人工授精で子どもを産む未来。実験都市・千葉では、さらにラディカルに性への管理は進められ、人工子宮によって男も出産でき、家族という概念がなく、人々は性欲を醜いものとしている。そして、その実験都市・千葉では男女関係なく、みな「おかあさん」と呼ばれるのだ。
ひきこもり論で有名な精神科医の斎藤環は、『消滅世界』の解説で正確に次のように述べる。
「そう、この社会ではすべてが女であり、すべてが母なのだ」[23]
そして、そのような社会を、いまの男と女はどう見ているのか?
「本書への反響として、女性の側からは主として「ユートピア小説」、男性からは「ディストピア小説」という評価があった。」[24]
この評価の乖離からもわかるのは、先ほど述べた通り、男は「女」というカテゴリーを必要とするが、女は「男」というカテゴリーを必要としないということだ。
『消滅世界』は現代の性と生を考えるうえで非常に有益な小説だが、私がこの小説で違和感をもったのは、その性欲への扱いだった。同書では、性欲を汚いものとして扱い、クリーンルームと呼ばれる部屋で、各々が性欲を自慰により処理することになっているが、そこには「性への歓び」がなく、その「歓び」が消えていく悲しみへの表現もない。これはもちろん、社会にとっては合理的だ。フランスの哲学者のミシェル・フーコーは次のように述べる。
「組織的に労働力を搾取している時代に、それが快楽の中で四散するなどということを人は許容できたであろうか」[25]
村田は徹底して合理的な社会を描いた。その社会には男も父も存在せず、セックスも存在せず、性欲は忌避すべきものとして扱われる。
しかし、それはあまりに性欲を見くびっていやしないか。
村田はレズビアン・セックスの可能性に一切ふれない。「女」しかいない「女」の「ユートピア」。そこでのセックスはおのずとレズビアン・セックスになる。「女」と「女」のセックス。それは挿入れないセックスだ。
斉藤は次のように言う。
「性行為は……男性の「所有原理」と女性の「関係原理」のすれ違いとして起こる。男性にとっての性交は、快楽であると同時に所有ないし征服のためのほぼ唯一の儀式でもある。性交後に態度が冷淡になる男性が多いのは、要は「釣った魚に餌はやらない」ということだ。これに対して女性にとっての性交は、関係原理を満足させるさまざまな行為の中の一つでしかない。それゆえ性愛関係=性交という「性交原理主義」は、男性原理に由来する」[26]
女は男と交流したいが、男は女を所有したい。そうすると「あなた〈と〉ひとつになりたい」という淡い欲望は女性特有のものであり、男性のそれは偽りだ、ということになる。なぜなら、男は「あなた〈と〉」(関係原理)ではなく、「あなた〈に〉挿入れたい」(所有原理)と望むからだ。「あなた〈と〉」を「あなた〈に〉」にしてしまうからだ。斎藤いわく、〈と〉(関係原理)と〈に〉(所有原理)の違いが性交を生む。
すると、村田は男性の所有関係(「あなた〈に〉」)を排除すると同時に、女性の関係原理(「あなた〈と〉」)をも、極端に狭めてしまったと思える。それは、レズビアン・セックス、すなわち、挿入れないセックスの可能性も奪ってしまったということだ。それは、おそらく、村田のセックス観の貧困に由来する。
同じくジェンダーレスの可能性を思わせる私小説・『夫のちんぽが入らない』もまた、女性に圧倒的に支持されているのも関わらず、セックス観において貧困だ。作者で主人公のこだまは、夫のちんぽが入らず、仕方がないので、「口や手」で交わる。
「「どうしてだろうね」と言っては手や口で出す日が続いた。私にできることはそれくらいしかない。農作業のようであった。」[27]
『夫のちんぽが入らない』はその題名にもかかわらず、性描写がほとんどない。せっかく挿入れないのだから、挿入れないセックス(レズビアン・セックス)の可能性を突き詰めればいいのに、と勝手に残念がっていた。実は、それを期待して購入したところがあるのだ。
というわけで、村田沙耶香にせよ、こだまにせよ、女性に支持される中年作家のセックス観は、二十歳も若い男性の私が言うのもなんだが、かなり貧困だ。
私は違和感を表明せざるを得ない。
なぜか。
さて、ここからは私の経験になる。
私は高校生のとき、はじめて「彼女」ができた。
で、彼女の家にお邪魔して、さて、童貞を卒業しようか、というときに、彼女のほうから「妊娠が怖いから、大学生になるまで、挿入れないで」とお願いされた。私もまた、それを承諾した。
それがよかった。
気持ちよかったのだ。
一晩中、裸でイチャついたりキスしたり胸をいじったりアソコをなめてただけで、指も(いま思えば奥手)、ちんぽもチツのなかに入れなかった。なので、ずっと欲情しっぱなしで、あれほど欲情と激しく濃く結託したことはないと思うほどだ。終わることがない。だから、「釣った魚に餌をやらない」ということもない。釣れない、終わらない、挿入れれない、から。欲情が収斂することなくつづき、キスしたりまさぐったりしている。終わるのは、射精したときではなく、疲れたときだ。
これは控えめに言っても(私は)かなり気持ちよかった。挿入していないのに。
しかし、彼女は大学生になっても、まだ妊娠を恐れ挿入れさせてくれなかった。そして私は挿入れさせてくれない彼女に嫌気がさして別れてしまった。単純に言えば、童貞を卒業したかったし、挿入れたかったし、〈男〉になりたかった。
それが不幸の始まりだった。
大学生になり、数人彼女ができて、挿入れるセックスをしても、幸せになれない。いくら挿入しても「うーん、なんか違うな」という気分はぬぐえなかった(すいません……)。私から見れば、相手も気持ちよさそうではない。でも、私はセックスは気持ちのいいものだと教わっていたし、大人の〈男〉と〈女〉のセックスは挿入れるものだと思っていたし、挿入れると気持ちよくなるのだと信じていたのだ。
挿入れないセックスがあるとは思えなかった。
実際には経験していたにもかかわらず、それをセックスだと思っていなかったのだ。
それは自分にも相手にも不幸なことだったと思うし、申し訳ないと思う。
そんなこんなで、なんだかなーと思っていたら、先日、女の子同士のレズ・セックスの映像をみてびっくりした。責められている女の人が、ほんとうに気持ちよさそうだったからだ。
「ああ! これこれ! こういうの!」と一瞬で納得した。
なにに納得したかはわからないが、とりあえず納得した。
ああ、いいなーと思った。男と女にもこういうセックスの可能性は開かれていいと思った。しかし、その納得が正しいのかどうか、いまは恋人もいないし、できる予定もないので、わからない。いつか、相手ができれば、ヤってみたいと思う。
いま私は正直、セックスのときの「ちんぽ」の使い道がよくわかっていない。もし、「ちんぽ」の使い道がわかり、「ちんぽ」で互いに気持ちよくなれれば、それは私の思想観・人生観に大きな影響を与えるだろう。
みなさん、聞いてみたい。ちんぽとその使用法はどのようなものか?
連絡先はcococooperative@gmail.comです。よろしくお願いします。
では、ごきげんよう。
そして、君と私のちんぽこ(まんぽこ)に幸あれ。
[1] 二村ヒトシ、『すべてはモテるためである』、イースト・プレス、2012、p.3
[2] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、pp.32-33
[3] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.163
[4] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.168
[5] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.167
[6] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.165
[7] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.165
[8] 実践性科学研究会、『ONANIE MANUAL』、データハウス、2003、p.8
[9] 実践性科学研究会、『ONANIE MANUAL』、データハウス、2003、p.10
[10] 金田淳子・澁谷知美『現代思想vol.47-2』「新たなる男性身体の〈開発〉のために」、青土社、2019、p.168
[11] 金田淳子・澁谷知美『現代思想vol.47-2』「新たなる男性身体の〈開発〉のために」、青土社、2019、p.167
[12] 村上春樹、『1Q84 BOOK1前編』、新潮社、2012、p.299
[13] 実践性科学研究会、『ONANIE MANUAL』、データハウス、2003、p.10
[14] 杉田俊介、『非モテの品格 男にとって「弱さ」とは何か』、集英社、p.35
[15] 杉田俊介、『現代思想vol.47-2』「ラディカル・メンズリブのために」、青土社、2019、p.115
[16] 森岡正博、『感じない男』、筑摩書房、2005、p.145
[17] 杉田俊介、『非モテの品格 男にとって「弱さ」とは何か』、集英社、p.23
[18] 実践性科学研究会、『ONANIE MANUAL』、データハウス、2003、p.9
[19] 野坂昭如、『エロトピア』、文藝春秋、1977、p.23
[20] 金田淳子・澁谷知美『現代思想vol.47-2』「新たなる男性身体の〈開発〉のために」、青土社、2019、p.176
[21] 二村ヒトシ、『すべてはモテるためである』、イースト・プレス、2012、p.94
[22] 森岡正博、『草食系男子の恋愛学』、メディアファクトリー、2008、p.167
[23] 村田沙耶香、『消滅世界』、河出書房、2018、p.277
[24] 村田沙耶香、『消滅世界』、河出書房、2018、p.277
[25] ミシェル・フーコー、『知への意志』、1986、新潮社、p.13
[26] 村田沙耶香、『消滅世界』、河出書房、2018、pp.279-280
[27] こだま、『夫のちんぽが入らない』、講談社、p.57
小峰くん自身の『臨(サイド)』の宣伝記事はこちら
note.com